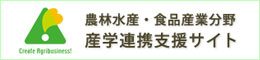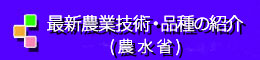東北地域農林水産・食品ハイテク研究会
事業計画
令和7年度 事業計画
1.企画委員会、役員会、総会、講演会の開催
1)企画委員会 令和7年6月18日(水)(オンライン)
2)役員会 令和7年7月16日(水)(仙台市)
3)第32回総会 令和7年7月16日(水)(仙台市及びオンライン)
4)講演会 令和7年7月16日(水)(仙台市及びオンライン)
2.産学連携支援に関わる各種事業の展開
わが国農林水産・食品産業の成長産業化を通じて、国民が真に豊かさを実感できる社会を構築するためには、農林水産・食品分野と異分野の連携により、革新的な研究成果を生み出すとともに、スピード感を持って事業化・商品化に導く必要がある。
そのため、農林水産省では平成28年度より新たな産学連携研究の仕組みである『「知」の集積と活用の場』を立ち上げ事業の展開を図っているところである。また、研究支援に関しては、平成30年度から「イノベーション創出強化研究推進事業」を立ち上げ、本格的な産学連携研究の推進と事業化・普及が試みられている。この事業は令和5年に研究成果の社会実装をより一層加速化するため、「オープンイノベーション研究・実用化推進事業」に変更された。東北管内からも多くの大学、研究機関が応募し、採択されて研究を展開している。さらに、令和元年度から開始された「スマート農業実証プロジェクト」では、東北地域から多くの取り組みが採択されている。スマート農業に関しては、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)」(令和6年10月1日施行)が策定され、その開発・普及に向けた体系的な体制が整備され、各種の事業が展開されている。
また、令和3年5月には、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少等の生産基盤の脆弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナを契機とした生産・消費の変化などの政策課題に対応すべく、将来にわたって食料の安定供給を図るため「みどりの食料システム戦略」が農林水産省から公表され、持続可能な食料システムを構築するための戦略が明確にされ各種の事業が展開されている。
こうした状況の中で、産学連携支援事業を推進するために当研究会では、農林水産・食品分野の高度な専門的知見を有する3名の中核型コーディネーター、12名の専門型コーディネーターを配置し、生産者、企業、研究機関との産学連携の支援に務めている。具体的には、『「知」の集積と活用の場』と連携しつつ、研究の初期段階から民間企業を含む産学官の関係機関が密接に連携した産学連携研究を促進するため、マッチング支援、競争的研究開発資金の獲得支援、研究成果の事業化・商品化支援等に重点を置き以下の事業を実施する。
| ・ | 生産者、農業法人、農業団体、市町村、普及センター、農業関連組織や民間企業へ訪問等を行い、技術的課題、研究開発ニーズ、普及支援ニーズを収集・把握する。 |
| ・ | シーズについては、農研機構東北農業研究センター(以下、東北農研)、東北地域の公立研究機関、大学、さらには民間企業を訪問して収集する。作物品種・栽培法に対する新たなシーズとしては、業務用米、超多収低アミロース米、新たな機能を持った米の品種、もち性の小麦やパン用小麦、多収で作りやすい大豆品種、東北地域での栽培適性をもったそば品種、水田複合経営を支えるタマネギ、子実トウモロコシなどの革新的な栽培法が注目される。 |
| ・ | 最近大きな注目を集めている技術としては、大規模水田作経営のさらなる規模拡大を促進する水稲の乾田直播技術、超低コストな子実トウモロコシの多収栽培技術、東北におけるタマネギの産地形成を支援する技術、イノベ事業に採択された無コーティング湛水直播技術、低アミロース米の多収技術と加工適性向上技術、さらには水稲の初冬直播栽培技術等があり、その普及に向けて積極的に支援していく予定である。 |
| ・ | 現在、スマート農業技術の開発・普及に関する事業の実施により、スマート農業技術に対する農業者・関連ベンチャー企業の関心は急速に高まっている。多くの農家は安価で手軽なスマート農業技術を求めている。こうした低コストで気軽に導入できるスマート農業技術(スモールスマート農業技術と呼ぶ)の開発・普及支援のために、関連するベンチャー企業等の情報を収集するとともにセミナー等を主催して、東北地域におけるスマート農業技術の開発・普及を支援していく。今年度は、特に夏イチゴのハウス栽培におけるドローンを利用した受粉技術について、セミナー・現地の取り組みの視察を通して普及を支援していきたい。 |
| ・ | また、みどりの食料システム戦略政策が今後強化されることから、地域資源の有効活用や循環、カーボンニュートラルの取り組み、さらには有機農業・土づくりへの取り組み情報を積極的に収集し、必要に応じてセミナー等で普及していく。 |
| ・ | 東北農研事業化推進室との月1回の定例の意見交換会、東北各地の専門型コーディネーターとの情報交換を緊密に行い、技術開発の状況、技術開発のシーズ・ニーズの把握に努める。 |
| ・ | 産学連携に関するニーズ・シーズの収集・提供については年間100件以上を、セミナーによるニーズ・シーズの提供については、提供する情報の内容に従って対面、ハイブリッド、オンライン等から有効な方法を選択して実施する。 |
2)産学連携等のためのマッチング
| ・ | 必要に応じ、JATAFFの「事業化可能性調査」制度の活用により、関係者によるワークショップやセミナーを開催し、競争的研究資金の獲得や研究成果の円滑な移転促進を図る。 |
| ・ | 東北農研育成の業務用多収米品種「ゆみあずさ」、多収で高温適性が高い直播栽培向き水稲品種「しふくのみのり」、東北ハイテク研も支援し岩手県農業研究センターが開発した超多収米(白銀のひかり)、水稲の初冬直播き、さらにはタマネギ、子実用トウモロコシの栽培技術の普及なども支援していく予定である。 |
| ・ | マッチングは、これまで、東北農研が育成したもち小麦品種「もち姫」を用いたうどん、餃子の商品化につなげるとともに、製パン適性に優れる小麦品種「夏黄金」の普及・商品化についても支援する予定である。 |
| ・ | 令和元年度に東北農研育成の大豆品種「里のほほえみ」を福島県相馬地域の農業法人に紹介するとともに、健康食品の製造販売企業との取引を仲介した。また、東北農研が開発した低コスト・自作可能なハウス環境遠隔監視システム(通い農業支援システム)については、スマート農業に関わるセミナーで紹介を行うとともに、興味をもった農家・農業法人への普及を支援している。現在、岩手県、青森県の農業法人、その他の農家に普及し、高い注目を受けている。「通い農業支援システム」は、農林水産省、「2021年農業技術10大ニュース」のトピック2に選ばれ高い評価を得ている。 |
| ・ | みどりの食料システム戦略政策の展開と関連した支援としては、下水汚泥処理によるコンポスト肥料を製造している企業の経営戦略作成を支援とともに、事業化資金の獲得を支援した。さらに、農林水産省が各地で実施している「グリーンサポート事業」の実証成果については、岩手県で実施された取り組みを紹介するためのセミナーを開催し、その成果・課題を整理して発信した。今年度は、宮城県、福島県、山形県の取り組みを東北農政局と連携して発信する予定である。 |
| ・ | また、木質資材の燃焼灰からカリ肥料を抽出して製品化して国産カリ肥料として供給するための研究プロジェクトが令和6年度から大学と企業が連携してスタートしている。このプロジェクトについては、競争的研究資金獲得だけでなく、研究内容・成果のPRを行い社会実装につなげていきたい。 |
| ・ | 福島県の放射能汚染地域復興のため、さつまいもを中心とした生産・加工を支援する取り組みを令和2年度から実施し、令和3年度は広く東北地域での生産可能性のPRを行った。農家の注目度が大きいことから、令和6年度に会津地域でセミナーを開催した。今後も東北地域におけるさつまいもの普及を目指して支援活動を継続していく予定である。 |
| ・ | その他の産学連携支援活動としては、ラズベリーの機能性解明に基づく商品化を目指す大学ベンチャー企業に生産者を紹介、高濃度気体溶解装置を開発した企業に「グリーンサポート事業」や水産関係や農業関係の専門家を紹介し、その普及に向けて支援する活動を昨年度から行っており、今年度も継続する予定である。 |
3)研究開発資金制度の紹介等
| ・ | セミナー等を開催し、農林水産省の競争的研究資金に係る制度の紹介、応募書類の作成等について指導・助言を行うとともに、個別相談会を年2回以上開催する。また応募相談に応じて、研究グループ参画機関の紹介、応募書類のブラッシュアップ等の指導・助言を行う。 |
| ・ | 令和6年度はオープンイノベ事業への申請、戦略的スマート農業技術の開発・供給事業への応募相談が少なかったため、今年度は応募が増加するよう、早くから研究機関・企業などに働きかけていく。 |
4)商品化・事業化の支援
| ・ | 令和5年度にもち小麦品種「もち姫」のさらなる生産拡大と多様な商品開発を目指してJA、製麺企業・製粉企業、地域特産品販売会社と連携して競争的研究資金(東経連ビジネスセンター)を獲得して商品化した「もちもち姫うどん」と「もちもち姫餃子」の更なるPRを行い、社会実装の成果をさらに拡大する取り組み支援を令和7年度も実施する予定である。今年度は、もち姫を利用した様々な食品をPRするため、生産地である紫波町でPRイベントを開催する予定である。 |
| ・ | また、オープンイノベ事業で昨年度から実施している木材燃焼灰の肥料化技術の開発については、研究成果のPRなど行い、研究の重要性を広く発信していきたい。初冬直播技術については、農家の注目度が大きいことから、機会をとらえてその有効性・技術の特徴をPRし、普及を加速化する予定である。 |
| ・ | 令和6年度のアグリビジネス創出フェアでは、新規就農者が開発した夏イチゴの加工品、北限のショウガとその加工品の紹介を行い好評であった。本年度は、東北農研が育成したパン用小麦品種「夏黄金」を利用した、各種のパンを紹介する予定である。 |
| ・ | コーディネーターによる民間企業・現場等のニーズを収集し、試験研究機関等に紹介してマッチングを図るとともに、必要に応じセミナー等を開催しマッチングの機会を設ける。 |
5)セミナーの開催
| ・ | 昨年度は、実践総合農学会・石川県と共催で地震・集中豪雨で被災した能登半島の現地でセミナーを開催した。多くの被災した農業経営者が参加し、乾田直播・初冬直播き・菌根菌利用技術などの最新の復興支援技術の利活用に関して講演・話題提供と意見交換を行い、農家から感謝された。また、これらの技術を現場で普及するため、石川県は、農林水産省が令和7年度に公募した「スマート生産方式SOP作成研究」に応募し、見事採択された。災害復興技術として普及することが期待される。 |
| ・ | また、東北農研と共催した「タマネギ栽培技術」「乾田直播・子実トウモロコシ栽培技術」セミナーは、農家を含め多くの関係者を集めて熱心な討論が行われた。令和7年度も要請があれば共催で開催する予定である。 |
| ・ | 令和7年度は8回程度の開催を目指してセミナーを企画する。内容的には、より問題を絞り込んだ新技術の開発情報、競争的資金獲得、商品化・事業化につながるような開発技術の社会実装に向けた産学連携セミナー、みどりの食料システム戦略の推進や農家が求めるスモールスマート農業の推進等の重要政策の展開を支援するようなテーマ、地域農業の持続的発展を支える革新技術の普及に関わるセミナーを開催したいと考えている。 |